【生成AI】最新版!2025年生成AI活用術 第2部
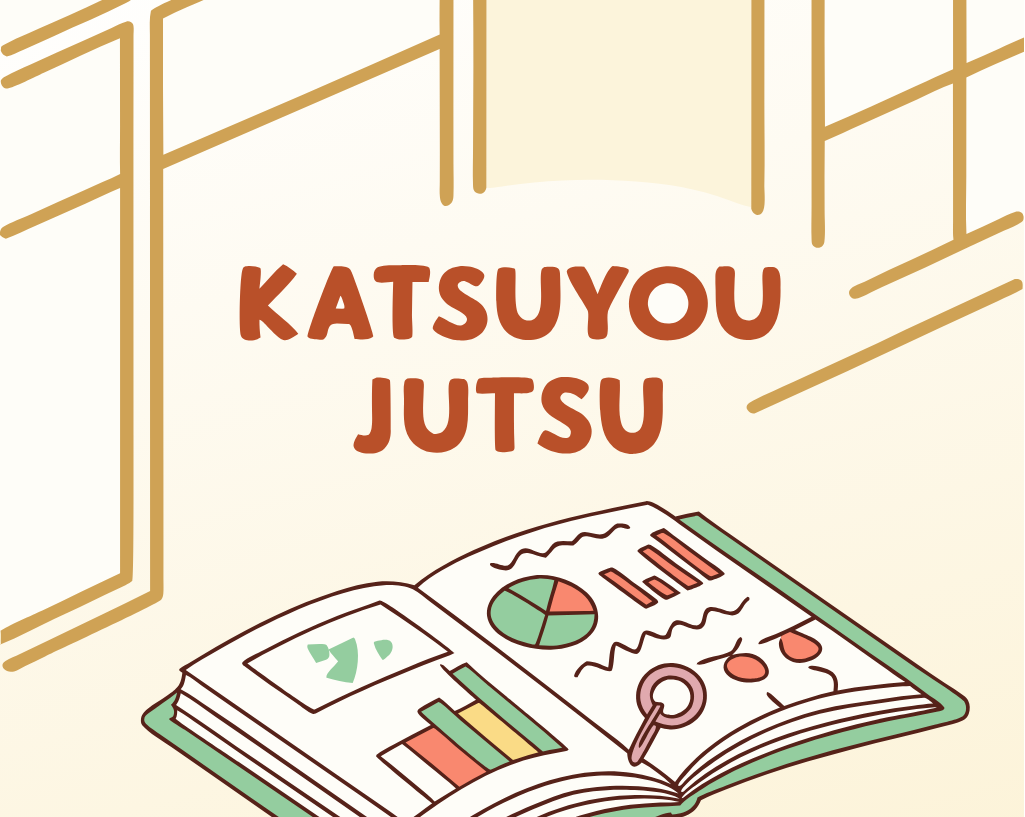
はじめに 〜生成AI、次のステップへ〜
こんにちは!IT支援部のにょっすです。
ChatGPT、Gemini、Claude、Copilot…
今や生成AIは、私たちの働く現場にすっかり定着し始めています。
一方で、
「うまく使いこなせていない気がする」
「結局、何が便利で何が難しいのか分からない」
といった声も多く聞かれます。
第2部となる今回は、「AIをどう使うと実務で本当に役立つのか?」という視点から、
プロンプト作成のコツや実践事例、社内導入の工夫などをじっくりご紹介していきます。
第1部がまだの方はこちらから是非チェックしてみてくださいね。
目次
1. 成果を左右する「良いプロンプト」の書き方
生成AIは“使い方”次第で可能性が無限に広がる一方、
“プロンプトの質”がそのままアウトプットの質に直結します。
◆ プロンプトとは?
プロンプトとは、「AIに与える命令文」のこと。
人間にとっての指示書、仕様書にあたるものです。
たとえば、こんな違いがあります。
| 悪い例 | 良い例 |
| このデータまとめて | このExcelブック内の全シートからB〜E列を読み取り、1行目を除いて集計シートに統合し、最後に「集計完了」と表示してください。 |
良いプロンプトの3原則は以下の通りです。
① 目的を明確に伝える
「なぜこの作業を依頼するのか?」という背景を伝えることで、AIはより的確な判断ができます。
② 条件・制約を具体的に書く
行や列の範囲、除外条件、形式指定などを丁寧に書きましょう。
③ 出力の形式を指定する
テキスト、リスト、コード、表形式など、アウトプットの形式も指定しましょう。
💡 ポイント:自然言語で書いてOKですが、なるべく簡潔にしましょう。
長すぎると文脈がぼやけ、AIが誤解する原因になります。
2. よくある失敗とその対策
生成AIを使っていると、しばしば次のような“つまずき”に出会います。
それぞれの原因と対処法を知っておくことで、ストレスを減らし、より効率的に活用できます。
失敗① 出力が意図と違う
原因:曖昧な指示・前提不足
対策:「誰に・何を・どのように」など、5W1Hを意識して具体化する
失敗② 途中で処理が止まる
原因:プロンプトが長すぎ、処理が複雑すぎる
対策:タスクを分解し、ステップごとにプロンプトを送る
例:まずはコードの構成案だけを出してもらい、その後コード本体を生成してもらう、など。
失敗③ 出力が冗長、またはざっくりすぎる
原因:出力形式の指定不足
対策:「表形式で」「150文字以内で」「JSON形式で」など明示的に指示
3. 活用シーン別おすすめプロンプト例
定型業務の効率化(経理・人事・営業など)
✦ メール文の下書き
「顧客に対して、請求書送付のリマインドメールを丁寧な敬語で200文字以内で作成してください。」
✦ 議事録要約
「以下の会議メモを5行以内で要約し、各発言者の立場も明記してください。」
✦ 社内文書のたたき台
「新入社員向けの研修マニュアルの目次を作ってください。対象は20代前半で、ITリテラシーは中程度です。」
Excel業務の自動化
✦ 関数の生成
「Excelで、B列(単価)×C列(個数)をD列(売上)に自動で計算し、E列には売上が10万円以上なら‘◎’と表示する関数を作ってください。」
✦ マクロの自動作成
「各支店シートのB〜E列を‘集計’シートにまとめるマクロを作成してください。処理が完了したら‘集計完了’と表示してください。」
✦ データチェック
「ExcelのA列に空白がある行を赤く塗りつぶし、B列に‘未入力’と表示するVBAを作ってください。」
コンテンツ・企画支援
✦ SNS投稿文
「税理士事務所のInstagram投稿を考えてください。テーマは『確定申告を早く終わらせる3つのコツ』。やわらかい文体で、絵文字も加えてください。」
✦ 提案書の構成案
「クラウド会計ソフト導入の提案資料の構成案を作成してください。相手は中小企業の経理担当者です。」
✦ アイデアブレスト
「会計事務所が中小企業に提供できる新しいサービス案を5つ考えてください。実現性と差別化ポイントも添えてください。」
4. 社内展開の工夫 〜AI活用を“文化”にする〜
生成AIは、個人が活用するだけでなく、チームや会社全体での定着が成果を大きく変えます。
◎ 小さな成功体験を共有する
Slackや朝会などで「AIで作ったこの資料、5分で終わりました!」と発信。成功事例の可視化が社内のムードを変えます。
◎ プロンプト集をナレッジ化する
よく使うプロンプトはテンプレート化し、Googleスプレッドシートなどで共有すると便利です。
◎ 社内勉強会の開催
「AI使ってみた会」「プロンプトの書き方講座」など、ライトな勉強会を定期開催すると習熟度が上がります。
💡 ポイント:強制より“ゆるく楽しく”が継続のカギ。小さな活用から、少しずつ広げていきましょう。
5. まとめ
生成AIは、決して「すべてを自動化する魔法のツール」ではありません。
“人間の判断や創造性を最大限に活かすための補助役”として活用することが、
本質的な意味での効率化につながります。
「定型作業はAIに任せる」
「人間は判断・対話・戦略に集中する」
この役割分担こそが、これからの働き方の大きなポイントになるでしょう。
生成AIの使い方は、まさに 『スキル』 です。
うまく使えば、生産性だけでなく仕事の楽しさも広がります。
弊社では、AIを始めとしたIT関連のお悩みを解決する『IT顧問』というサービスを行っております。
普段PCを使う中で気軽に相談できる相手が欲しい、
トラブルがあった際に対応してほしい、AIの勉強会を定期的に開いて欲しい等
IT関連のお悩み事がある場合はぜひ弊社にお問い合わせください。
こんなことでもよいのかな、というレベルでも全く構いませんので、
まずはこちらからご相談頂ければと思います!
最後まで読んでいただきありがとうございました。
それでは次回もよろしくお願いいたします!

 ©︎ 2026 Back Office Solution Inc.
©︎ 2026 Back Office Solution Inc.